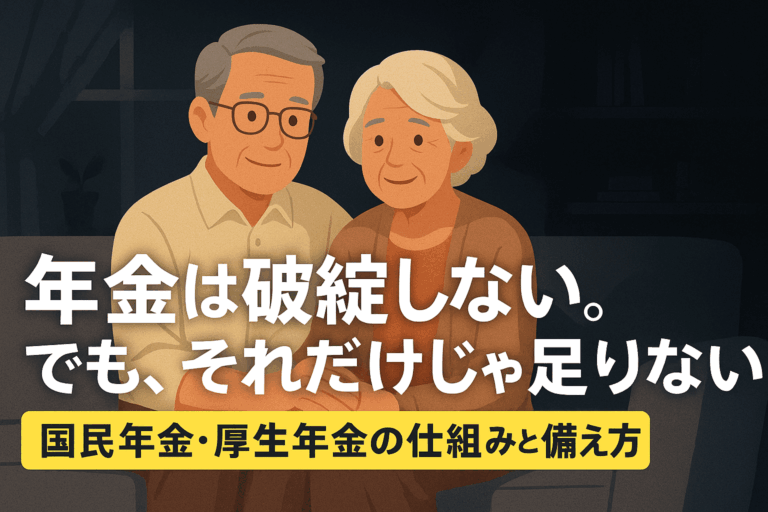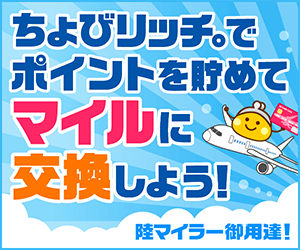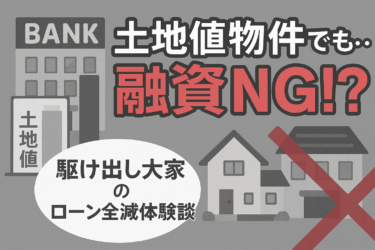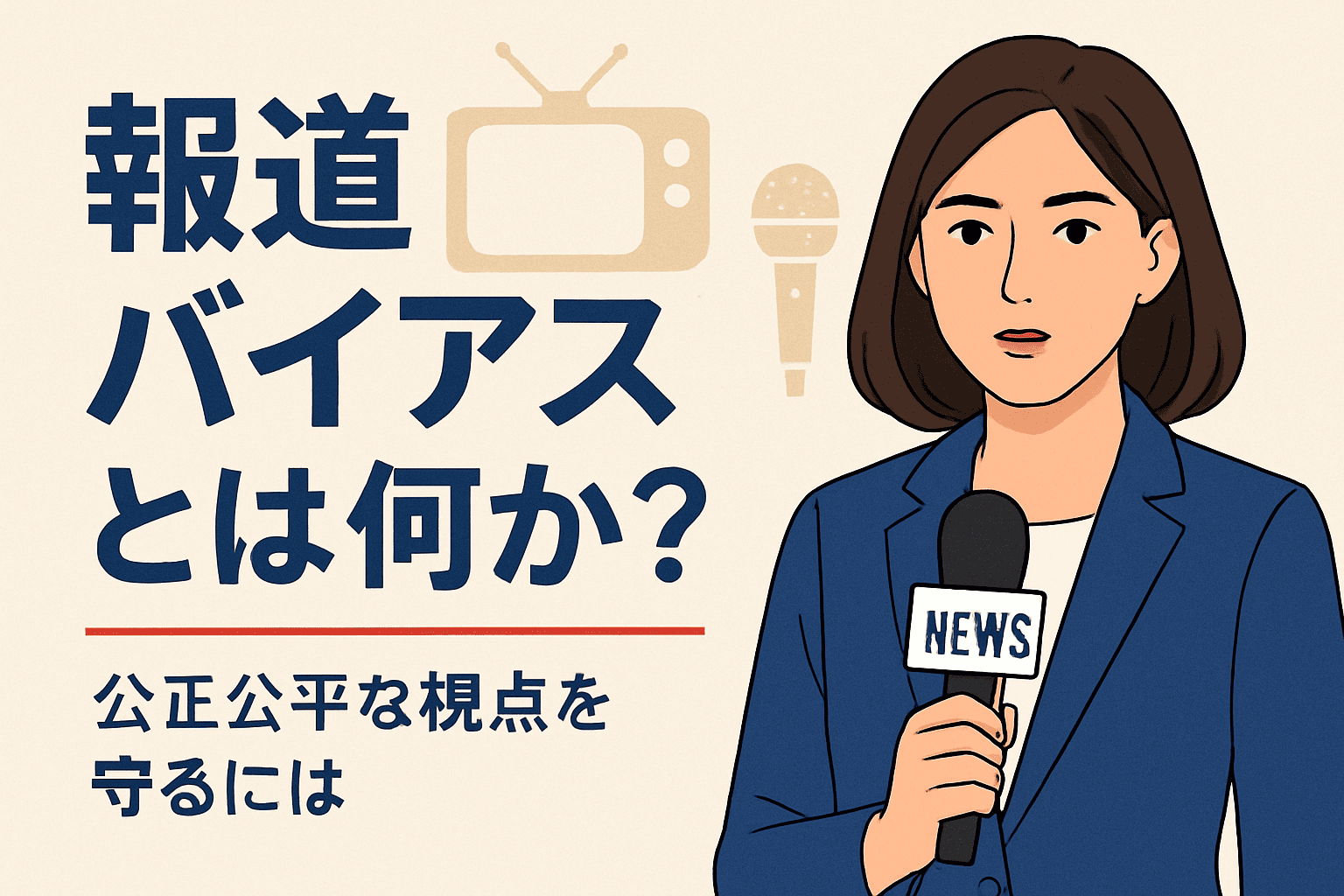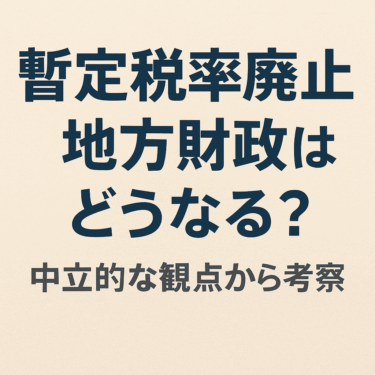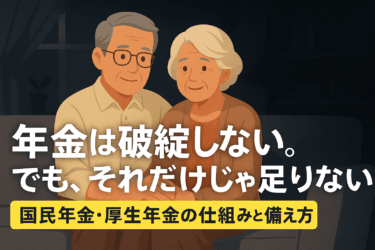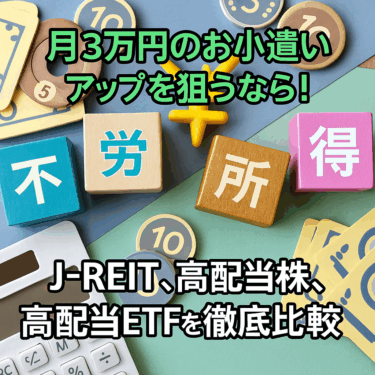「年金って、将来ほんとにもらえるの?」そんな声を、よく耳にします。テレビでもネットでも「年金はもう破綻する」といった話が広まっていますよね。ですが、実はそれ、本当ではありません。今回は年金がどういうしくみなのか、なぜ「破綻しない」のか、そして「それだけでは足りない」と言われる理由を、できるだけわかりやすく、丁寧に解説していきます。
年金ってどんな種類があるの?制度のしくみを整理しよう
公的年金の2本柱
※補足:この他に、企業によっては「企業年金(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金など)」を設けているところもあります。これは公的年金に上乗せして支給されるもので、企業ごとの任意制度です。
- 国民年金:自営業・フリーランス・学生など、すべての人が20歳になったら入る「基礎的な年金」。
- 厚生年金:会社員や公務員が、国民年金に上乗せする形で加入する年金。保険料も多く払うが、そのぶん将来もらえる額も多くなる。
この2つを合わせて「公的年金」と呼びます。
公的年金の仕組みは「賦課方式」
- 今の現役世代が払った保険料が、今の高齢者への支給に回されるしくみ
- 積み立て式ではないため、「もらう頃にお金が尽きている」という形では破綻しない
- 支給額や仕組みの調整で維持されていく
だから、「年金が破綻する」と聞いても、仕組みを知るとそのイメージは少し違って見えてくるはずです。
「100年安心」って本当だったの?
2004年の制度改革とその前提
- 政府が「100年安心の制度です」とアピール
- でも当時の想定は「出生率は回復する」「給料も上がっていく」など、現実とずれた前提が多かった
なにがどうズレたのか?
- 子どもは思ったより生まれず、働く世代も減少
- 賃金も停滞し、保険料の負担が重く感じられるように
制度そのものが壊れたわけではないけれど、「楽観的な前提が外れた結果、現実とのギャップが生まれた」というのが実態です。
年金って運用されているの?減らないの?
年金積立金の運用とは
- GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が株や債券に投資
- 将来の支払いに備えて、お金を「増やす努力」もしている
最近の運用状況は?
- 短期的には米国株の下落でマイナスの年もある
- でも長期では累計収益100兆円超。運用成績としては極めて良好
「使うだけじゃなく、増やす努力もちゃんとされている」というのは、もっと知られてよいポイントです。
年金だけで暮らせるの?
減り続ける“受け取る額”
- 少子高齢化が進むと、支給する側が減り、受け取る側が増える
- 「マクロ経済スライド」によって、年金額は物価などに応じて調整され、実質的に少しずつ減る方向
実際どうなる?
- 年金は「最低限の生活」を支えるレベルが基本
- 家賃・医療費・食費をすべてカバーできるとは限らない
つまり、**「制度は壊れないけど、それだけで暮らせるとは限らない」**というのがリアルな姿です。
じゃあ将来どう備えればいいの?
自分でできる備え方
- 「iDeCo」や「つみたてNISA」など、税金を抑えて資産形成できる制度を活用する
- 少額でも若いうちから始めると将来大きな差になる
公的年金とiDeCoの違い
- 公的年金:国が制度として運営し、全国民が加入する義務がある
- iDeCo(個人型確定拠出年金):加入は任意で、自分が積み立てた分がそのまま運用され、将来自分に戻ってくる
ポイント:iDeCoは「自分年金」。積み立てるかどうかも金額も自分次第で、公的年金とは真逆の“自己責任型”の制度です。
公的年金とつみたてNISAの違い
- 公的年金:生活保障を目的に最低限を支えるしくみ。賦課方式で他人が支えてくれる仕組みでもある
- つみたてNISA:投資で増やしたお金がそのまま自分に返ってくる。運用成果が全て自分次第という点で、iDeCoと同様「積み立てた分が自分に戻る」構造
ポイント:つみたてNISAは、将来の選択肢や生活の自由度を増やすための「貯蓄と投資の枠」。年金とは目的も性質も異なりますが、うまく併用すれば力強い味方になります。
ライフスタイルの工夫もカギ
- 定年後も少し働けるような準備やスキルアップ
- 支出を見直して、無理のない生活設計を
「年金があるから安心」ではなく、「年金をベースに、プラスαで備える」発想が大切です。
最後に:制度は生きている、理解と備えがカギ
「年金はなくならない」けれど、「それだけでは足りないかもしれない」。だからこそ、大事なのは「知って、考えて、動く」ことです。
難しいことばかりに感じるかもしれませんが、今のうちから少しずつ理解していけば、将来に不安を感じすぎることなく、準備ができます。
制度を信じるためにも、まずは制度を知ることから。この記事がその一歩になればうれしいです。