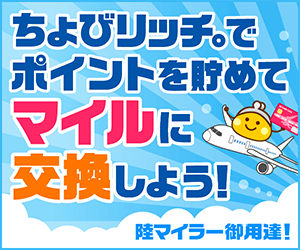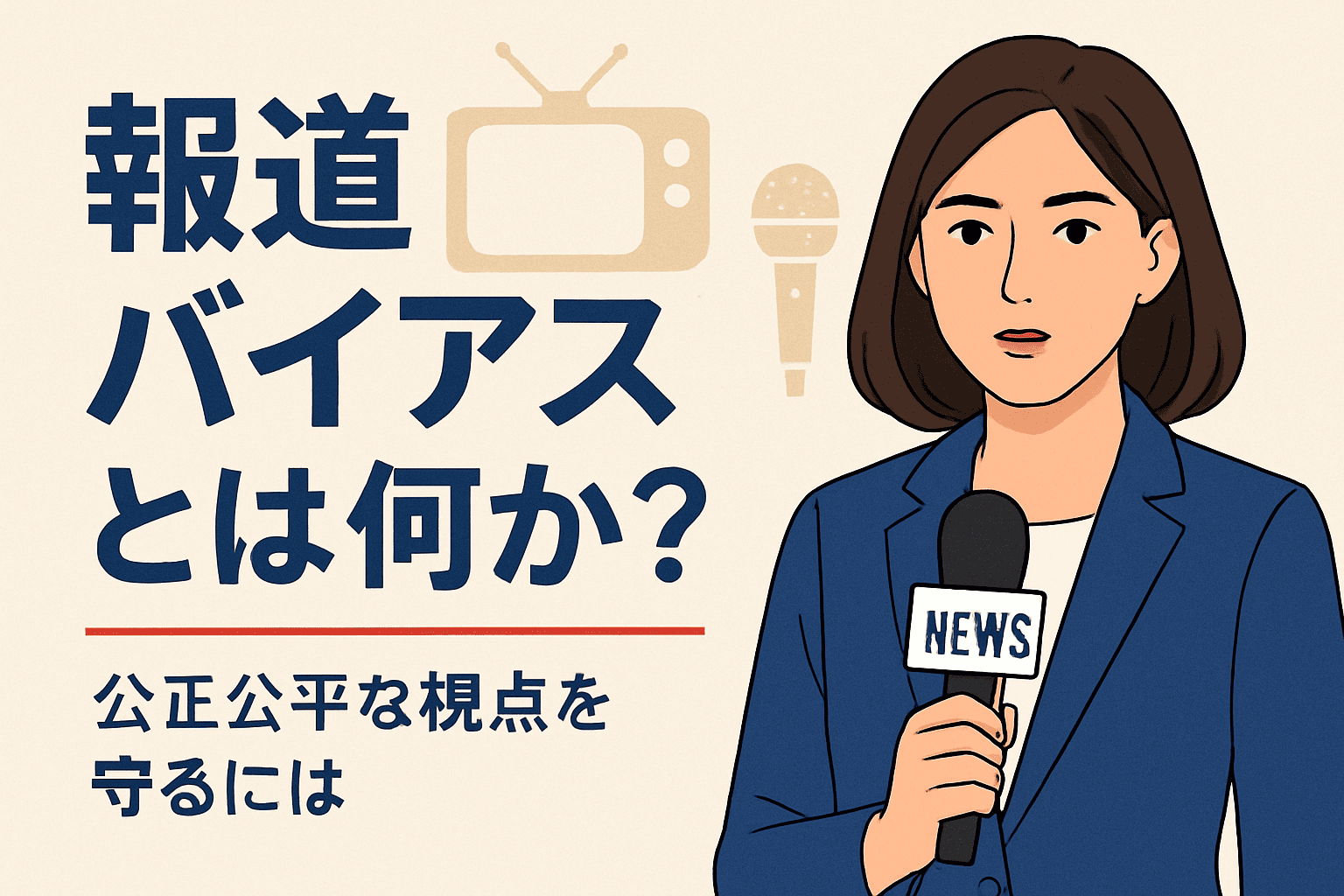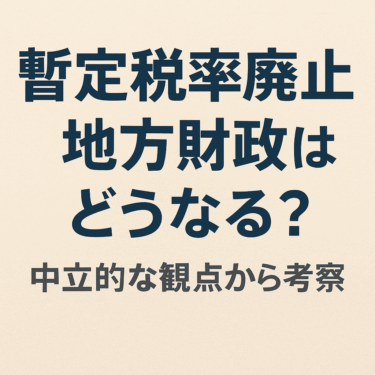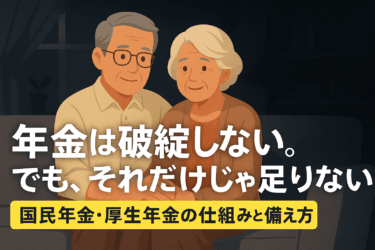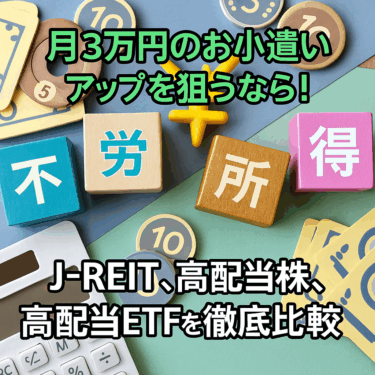はじめに
「景気は回復基調」「企業の業績は堅調」「賃金も上昇傾向」──
そんな経済ニュースが身の回りを飛び交う一方で、「なぜか自分の生活は苦しくなるばかり」と感じている人は少なくありません。
これは単なる個人の錯覚ではなく、むしろ経済的な構造そのものの問題です。
日本は今、物価が上昇しているにもかかわらず、賃金や雇用の実態が伴わず、経済成長も実感できない「スタグフレーション(stagflation)」の入口に立たされています。
あるいは、氷河期世代など一部の層から見れば、すでにその渦中にあると言っても過言ではないでしょう。
本稿では、この“見えにくい不況”の正体を、生活者目線と経済構造の両面から探っていきます。
スタグフレーションとは──成長なき物価上昇
スタグフレーションの定義と発生メカニズム
スタグフレーションとは、景気が停滞しているにもかかわらず物価が上がるという、通常は共存しにくい経済現象です。
本来、インフレは景気の過熱や需要の増加とともに起こるものですが、スタグフレーションでは景気低迷と物価上昇が同時に進行します。
日本における現在の兆候
2020年代以降の日本では、エネルギー価格や輸入コストの高騰によるコストプッシュ型インフレが進む一方、賃金は十分に伸びず、消費は低迷。
景気実感が伴わないまま、物価だけが上がり続けるという「見かけだけの好況」が広がっています。
ただし現時点では、総合的な失業率は低く、新卒採用や大企業社員を中心に賃金上昇の動きも見られます。
このため、「社会全体にスタグフレーションが波及した」とまでは言い切れず、「一部の層がすでにスタグフレーションに陥っている」または「コストプッシュ型インフレが引き金となりつつある段階」と表現するのが現実に近いでしょう。
実感としての貧しさ──可処分所得の減少
可処分所得とは何か
家計が感じる「苦しさ」の要因は、名目賃金ではなく「可処分所得」にあります。
可処分所得とは、給与から税金や社会保険料を差し引いた後、実際に生活に使えるお金のことです。
名目上の収入が微増しても、それ以上に物価や各種負担が増えれば、実際の購買力は下がるため、生活が苦しくなったと感じるのは当然の結果です。
実質賃金と生活コストの乖離
実際に厚生労働省の統計でも、実質賃金は2022年以降、前年比でマイナスが続いています。
食料品、光熱費、家賃など生活必需品を中心に価格が上がる一方で、賃金の伸びはそれに追いつかず、家計の実質的な自由度は年々縮小しています。
可処分所得の減少は、単なる“気のせい”ではなく、数値として裏付けられた現象です。
これは、所得層を問わず広く起こっている「体感的不況」の根拠ともいえるでしょう。
いまはスタグフレーションなのか?──判断が難しい理由
指標が示す“表向きの景気回復”
- 株価は上昇:企業収益や投資家心理を反映し、「成長しているように見える」データ。
- 失業率は低水準:一見、雇用が安定しているように見える。
しかし生活の実態は…
- 実質GDPは低迷:個人消費や設備投資の伸び悩み。
- 賃金上昇は一部に限られる:新卒や大企業社員には波及しても、中小企業や非正規には届かない。
- 氷河期世代を中心に生活はむしろ悪化:物価だけが上がり、実質所得は目減り。
つまり、「誰にとってスタグフレーションなのか」は層によって異なり、 全体としてのスタグフレーションではなく、“部分的スタグフレーション”として進行しているのです。
経済政策が悪循環を引き起こす
緊縮財政の弊害
この苦しさに拍車をかけているのが、日本の財政・経済政策です。
消費税増税、社会保険料の上昇、実質的な賃上げを伴わない補助金政策──いずれも、可処分所得を押し下げ、消費を冷え込ませています。
財政健全化路線の限界
「財政健全化」を掲げる緊縮路線は、むしろ景気の回復を遠ざけ、スタグフレーションの温床となりかねません。
氷河期世代にとっては“今さら始まったことではない”
長期的に続いてきた経済的困難
1990年代後半から2000年代初頭に社会に出た氷河期世代は、長期にわたって景気低迷と非正規雇用を強いられてきました。
不況の実感はすでに日常
つまり、彼らにとっては「今さら始まったスタグフレーション」ではなく、
「ずっと続いていた経済的苦境が、今になって“コストプッシュインフレ”というかたちで表出してきた」
という認識に近いのです。
脱却の鍵は「人と生活」への投資
可処分所得を増やす政策とは
今必要なのは、数字や財政黒字を優先する政策ではなく、 「生活者の実態に即した財政出動と支援」です。
- 社会保険料の一時軽減
- 消費税の時限的引き下げ
- 公共部門(医療・福祉・教育など)への再投資
内需を刺激するために
これらは、可処分所得を増やし、内需を活性化させ、 景気回復を実感ベースで支えるための現実的なアプローチです。
結論:静かに進行するスタグフレーションを見逃すな
今の日本は、「表向きは好景気、しかし体感としては不況」という分断した構造の中にあります。
スタグフレーションは突発的に顕在化するものではなく、
じわじわと生活を圧迫し、気づいたときには抜け出せなくなる“静かな不況”
です。
特に氷河期世代のように、構造的な不遇を経験してきた層の実態にこそ、 いまの日本が直面している“歪な成長”の本質が現れています。
経済の回復とは、株価やGDPの数字だけで測るものではなく、 一人ひとりの生活実感をもってして初めて成立する。
それを見失っては、いつまでも「出口なき不況」から抜け出すことはできません。