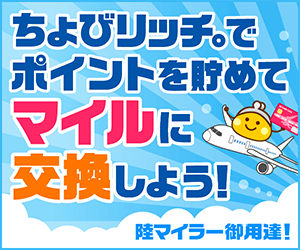「遺言書さえ書いておけば安心」──
そう思っていませんか?
実は、間違った形式の遺言書や中途半端な準備が、
かえって家族間の深刻な争いを引き起こしてしまうケースが後を絶ちません。
特に、
-
自筆証書遺言を書いたが形式に不備があった
-
内容に疑念を持たれ、裁判に発展してしまった
-
「検認手続き」や「遺言無効訴訟」で家族が消耗してしまった
──そんな現実を、私たちは冷静に受け止めなければなりません。
だからこそ今、
ただ「遺言書を書く」だけではなく、「正しい方法で遺す」ことが求められています。
この記事では、
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、
それぞれのメリット・デメリット、
そして「家族の未来を守る」ために選ぶべき最適な道を
できるだけわかりやすく解説していきます。
家族に、無用な争いを遺さないために。
今、正しい一歩を踏み出しましょう。
【第1章】はじめに──「うちは大丈夫」と思っていませんか? 「うちは財産もそんなにないし、兄弟仲も悪くないから大丈夫!」──そんなふうに思っている方、多いんじゃないでしょうか? 実は、相続トラブルの大半は資産5000万円以下の一般家[…]
【第1章】遺言書を書きたいと思ったら最初に知っておくべきこと

遺言書には3種類ある(自筆・公正証書・秘密証書)
「遺言書を作りたい」と考えたとき、まず知っておくべきなのが、遺言書には主に3つの種類があるということです。
- 自筆証書遺言:全文を自分の手で書く形式。費用がかからず手軽だが、方式の不備や保管ミスのリスクがある。
- 公正証書遺言:公証人が作成し、原本を保管する形式。費用はかかるが、信頼性と実効性が非常に高い。
- 秘密証書遺言:内容は本人のみが知る形で、封印したものを公証役場で確認してもらう。現在ではあまり利用されていない。
このうち、実務で使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが中心です。
それぞれの方式の違いと基本ルール
自筆証書遺言は、以下のようなルールに沿って書く必要があります:
- 本文、日付、署名、押印をすべて自筆で記載する
- ワープロや代筆は不可
- 複数ページある場合はすべてに署名・押印が必要
一方、公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成されます。
- 本人が口頭で内容を述べ、公証人が文章化
- 原本は公証役場で保管され、改ざんや紛失のリスクがない
- 証人には相続人や利害関係者はなれない
つまり、公正証書遺言は「正しく残すこと」が制度的に保証されている一方で、自筆証書遺言は自己責任の色合いが強い制度なのです。
遺言書を放置するリスクとは?
「まだ元気だから」と遺言作成を後回しにしていると、次のようなリスクが発生します:
- 認知症などで判断能力を失うと、そもそも作成できなくなる
- 自筆証書遺言を作っていたとしても、書式不備で無効扱いされる可能性がある
- 死後に遺言書が発見されず、遺産分割協議が紛糾する
また、特に自筆遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。検認手続きには1〜2ヶ月以上かかることもあり、その間に相続手続きがストップしてしまうケースも少なくありません。
「書くのはいつでもできる」ではなく、 **「書けるうちにしか書けない」**という意識が、相続対策ではとても大切です。
【第2章】自筆証書遺言──手軽だけどこんな落とし穴も

自筆証書遺言のメリットとデメリット
【メリット】
- 自分ひとりで作成できる
- 費用がほとんどかからない
- 思い立ったときにすぐ書ける
【デメリット】
- 形式に厳格なルールがあり、ミスがあると無効になる
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
- 紛失・改ざんのリスクがある
- 相続人の間でトラブルの火種になりやすい
無効になる典型的なパターン
- 日付の記載がない、または曖昧(例:「令和6年春」)
- 署名がない/押印を忘れた
- 他人の代筆が含まれている
- 財産の記載が不明確(例:「預金全部」など)
こうした形式的な不備により、せっかく遺言書を書いても無効とされる例は少なくありません。
家庭裁判所での検認手続き
自筆証書遺言を有効に使うには、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本や住民票を揃え、裁判所に提出
- 検認期日までに1〜2ヶ月かかることも
- この間、銀行口座の凍結解除や不動産名義変更などの相続手続きが進められない
また、遺言書の保管場所が不明だったり、検認前に開封してしまったりすると、余計なトラブルの原因にもなります。
自筆証書遺言は争いを呼びやすい?
たとえ形式が正しくても、自筆遺言は「争点の材料」になりやすい側面があります。
- 相続人が「無理やり書かされたのでは」と主張しやすい
- 筆跡や内容の不自然さを理由に無効を争う訴訟に発展する例も
- 家庭裁判所の検認は形式の確認だけで、内容の妥当性までは保証しない
また、現代ではペーパーレス化が進んでいるため、筆跡鑑定に使える本人の自筆サンプルがそもそも存在しないというケースも珍しくありません。メールや電子署名が主流となり、紙に手書きする機会そのものが減っているため、遺言書が発見されても「本当に本人が書いたのか」を立証できず、争点となる可能性があります。
さらに、加齢とともに筆跡が変わってしまうリスクもあります。握力の低下や関節疾患などにより、同じ人物であっても20年前と現在ではまったく異なる字になることもあり、鑑定結果が分かれることも。
具体例:筆跡が争点になったあるケース
70代の男性が自筆証書遺言を残して亡くなったが、相続人の一部が「本当に父が書いたのか」と疑い、筆跡鑑定を請求。ところが、比較できるのは20年以上前の年賀状や履歴書しかなく、鑑定人の意見は「同一人物と断定するには資料が不足している」とあいまいな結果に。
納得できなかった兄弟が無効主張を展開し、訴訟に発展。最終的に家族関係は完全に決裂してしまった──という実例もあります。
こうした事態を防ぐには、「そもそも筆跡の真偽を争う必要のない形式」、つまり公正証書遺言を選んでおくことが、もっとも確実で、家族を守る選択になります。
弁護士チェック付きでも“中途半端”になりやすい?
実際には、自筆証書遺言を弁護士がチェックした場合でも、その後の検認手続きや執行において家族が戸惑う場面は多く見られます。
- 弁護士が原案を作成しても、本人が書き写す段階でミスが生じる可能性
- 死後の手続きについて家族に伝わっていないと、検認の際に混乱する
このように、作成時点では安心していても、死後の“実務”で想定外の問題が起きるのが自筆遺言の落とし穴です。
【第3章】公正証書遺言──トラブル防止の最適解
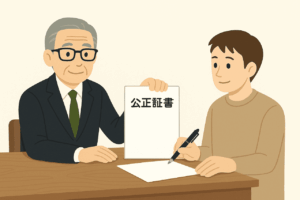
公正証書遺言とは?(制度・作成方法・基本の流れ)
公正証書遺言は、遺言者が公証人役場で口頭で遺言の内容を伝え、それを公証人が文章化し、証人2名の立会いのもとで作成される公文書です。
- 公証人が作成するため、法的に無効となるリスクが限りなく低い
- 原本は公証役場に保管されるため、改ざん・紛失・発見漏れの心配がない
- 証人2名の立会いがあることで、第三者の確認が自動的に組み込まれる
公正証書遺言のメリット(検認不要・改ざん防止)
- 家庭裁判所での検認が不要のため、死後すぐに手続きが開始できる
- 相続人間で「この遺言は本当に有効なのか?」といった無効主張の余地が極めて小さい
- 書式や法律要件を公証人が確認・作成するため、作成時点から法的整合性が担保される
公正証書遺言は「家族の絆」を守る
相続トラブルは、単に財産の分け方を巡る争いにとどまりません。 感情的な対立が深まると、兄弟姉妹の縁が切れる・親族との関係が完全に壊れることもあります。
しかし公正証書遺言では、
- 内容が明確かつ法的に有効であることが保証されている
- 争点がそもそも少ない
ことから、対立が深刻化せず、関係修復不能に至らない可能性を高めることができます。
「トラブルの火種を残さない」ことこそが、家族の未来を守る最良の方法なのです。
公正証書遺言は「元気なうち」に作るべき理由
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思確認を直接行うことが義務づけられており、 この確認が取れないと作成できません。
つまり、
- 認知症を発症したあと
- 医師の付き添いや通訳が必要な状態
- 筆談すら困難な身体状況
といった場合には、遺言自体が作れなくなる可能性が高くなります。
また、相続人など利害関係者は同席できないため、親族の付き添いが不可である点も、早めに動くべき理由の一つです。
弁護士・司法書士サポートの違いと費用感
公正証書遺言の作成は、本人が単独で公証役場に赴き、直接依頼することも可能ですが、 実際には多くのケースで専門家(弁護士または司法書士)のサポートが利用されています。
| サポート形態 | 特徴 | 想定費用 |
|---|---|---|
| 弁護士+公正証書遺言 | 遺留分・トラブル対応まで視野に入れた設計が可能 | 20万〜30万円程度+公証人費用 |
| 司法書士+公正証書遺言 | 財産目録や書類の整理中心。作成支援に強い | 10万〜20万円程度+公証人費用 |
一見、**弁護士+自筆証書遺言(弁護士が原案作成)**という選択肢もありそうに見えますが、
- 結局、書き写しミスが起こるリスク
- 死後に検認が必要な手間
- 相続人への伝達・保管方法の不安
を考えると、多少費用がかかっても最初から公正証書で仕上げる方が実務的といえます。
専門家の報酬は“価格”だけで選ばない
「なるべく安く済ませたい」──気持ちは自然です。 ただし、専門家の報酬は事務所ごとの経験値や得意分野に大きく左右されます。
- 高額だから安心とは限らない
- 安価だから悪いとも限らない
- 弁護士・司法書士という肩書きで選ぶのではなく、
✅ 「相続・遺言に強い実務経験があるかどうか」
✅ 「その専門家が情報発信や事例紹介をしているか」
といった“中身”を見て選ぶことが、結果的に家族の安心につながります。
※以下は2025年5月1日時点の情報に基づきます。
公正証書遺言の費用はこう決まる
公正証書遺言の作成にかかる費用は、主に以下の3要素に分かれます。
| 項目 | 内容 | 目安金額 |
| ① 公証人手数料 | 相続財産の額に応じて定められた法定料金 | 下記表参照 |
| ② 証人費用 | 公証役場が手配する場合、1名5,000〜10,000円程度 | 約1〜2万円 |
| ③ 専門家報酬(任意) | 弁護士や司法書士に作成支援を依頼した場合の報酬 | 10〜30万円程度 |
公証人手数料 早見表(法務省基準)
| 相続財産の額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万超〜1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 43,000円+13,000円 ×(5,000万円ごと)加算 |
| 3億円超〜10億円以下 | 上記に加え11,000円ずつ加算 |
| 10億円超 | 上記に加え8,000円ずつ加算 |
※別途、出張費・写し交付などの加算が必要な場合あり。
【参考例】
相続財産が1.5億円の場合の公証人手数料:
- 1億円まで:43,000円
- 超過5,000万円(13,000円 × 1)=13,000円
- 合計:56,000円(+税)
それは単なるコストではなく、“安心の保険料”かもしれません。
【第4章】遺言書の準備は“ここ”から始めよう
ステップ1:財産の“棚卸し”をしてみよう

遺言書を作るうえでまず大切なのは、自分の財産が「どれだけ、どこに、どうあるか」を正しく把握すること。これを**“財産の棚卸し”**と呼びます。
【主なチェック項目】
- 預貯金(銀行・証券口座ごと)
- 不動産(土地・建物/持分など)
- 自動車、貴金属、美術品、骨董などの動産
- 株式・投資信託・暗号資産などの金融資産
- 借入金、連帯保証、負債の有無
- 誰にも知られていない“隠し財産”がないか
棚卸しの段階では金額評価までは不要です。 まずは「何を持っているか」を全体像としてまとめておくことが大切です。
💡 特に近年注目の“新しい相続財産”の扱い方
財産の多様化が進むなかで、評価や継承の方法に注意が必要なものも増えています。
【1】相続財産として明確に扱われるが、価格変動が激しいもの(=高ボラティリティ資産)
- 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム等)
- 株式や新興市場の投資信託
これらは相続時点での市場価格をもとに課税・評価されますが、 価格変動が大きいため「相続時にいくらだったか」の記録と、 ウォレットの情報・秘密鍵・ログイン方法の整理が極めて重要になります。
【2】価値評価が困難な“マニア・限定資産”
- NFT(非代替性トークン)
- トレーディングカード(例:ポケモンカード、MTG(=マジック・ザ・ギャザリング)など
- コレクター向けのゲームソフト、プレミア品
これらは一見無価値に見えても、数十万円以上の評価がつくケースもあり、 特に家族がその価値を知らないと「ただのガラクタ」として処分されてしまうリスクがあります。
こうした資産は、
- 「どこに何があるか」
- 「どのくらいの価値があるのか(相場のURLなどでもOK)」
- 「特定の人に遺す意図」
を遺言書本体または別紙メモで残しておくことで、相続人による誤解や処分リスクを避けられます。
ステップ2:家族構成と“遺す相手”の確認
次に、自分の法定相続人が誰になるかを確認します。これも遺言を作るうえでの基本です。
【確認ポイント】
- 配偶者は常に相続人になります
- 子がいる場合は、子が相続人(複数いれば法定割合で分ける)
- 子がいない場合は、親 → 兄弟姉妹の順で相続人になります
- 養子縁組や認知した子、代襲相続の対象なども要確認
ステップ3:「どう遺したいか」の方向性を考える
法定相続のルールを前提としつつ、遺言によって意思を明確にすることで、次のような希望を叶えることができます:
- 特定の子に事業や不動産を相続させたい
- 面倒を見てくれた家族に多めに渡したい
- 相続人以外の人(内縁の妻、友人など)にも財産を渡したい
- 家族や介護スタッフへ感謝のメッセージを添えたい
こうした希望は、遺言書に明記することで初めて実現可能になります。
ステップ4:作成形式を選ぶ(自筆 or 公正証書)
前章までで紹介した通り、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。 それぞれの特徴を踏まえて、自分に合った形式を検討しましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 手軽さ | ○ | △(手続きが必要) |
| 費用 | ◎(ほぼ無料) | △(数万円〜) |
| 法的安定性 | △(方式ミスで無効の恐れ) | ◎(確実に有効) |
| トラブル回避 | △(争いになりやすい) | ◎(争いにくい) |
公正証書遺言を選ぶ場合は、
- 財産の棚卸し資料
- 家族構成と希望のメモ
- 本人確認書類 などを持参し、公証人役場や専門家へ相談に行くのが一般的です。
まとめ:第一歩は「現状を見える化」すること
遺言書の準備は、何か特別な書類を書き始めることではありません。
✅ 自分の財産と家族構成を見直す
✅ 「誰に何をどう残したいか」を少し考える
──これだけでも、もう“半分は準備できた”と言えるのです。
【第5章】遺言書がある場合・ない場合で何が変わる?

まずは比較表でざっくり把握
| 項目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
|---|---|---|
| 相続手続き | 遺言内容に沿って手続き可能 | 相続人全員で協議しないと進まない |
| 不動産の名義変更 | 単独相続が可能(遺言で指定されていれば) | 全員の合意+書類+実印が必要 |
| 相続争いの可能性 | 大幅に低下(遺言が有効なら) | 高確率でトラブル発生 |
| 財産配分の自由度 | 相続人以外にも遺贈可能 | 法定相続人のみに限定 |
| 家族の心理的負担 | 「故人の意思が明確」と安心感 | 「どう分けるか」で関係悪化リスク大 |
ケース1:「不動産を長男に相続させたかったが…」
【遺言書がある場合】
- 「自宅の土地建物は長男〇〇に相続させる」と明記されていれば、他の相続人の同意不要で名義変更可
- 相続手続きはスムーズに完了し、居住や売却にも支障なし
【遺言書がない場合】
- 長男が住み続けていても、「他の兄弟の持ち分がある」とされる
- 兄弟から「売却して現金で分けて」と言われると対応困難に
- 最悪の場合、共有者間でのトラブルから裁判沙汰へ
ケース2:「生前世話になった嫁に少しでも残したい」
【遺言書がある場合】
- 「配偶者の母□□に金銭100万円を遺贈する」と書いておけば、相続人でなくても受け取れる
- 法的に有効な文面なら誰にも異論を挟まれず実行可能
【遺言書がない場合】
- 相続人以外は何も受け取れない
- 感謝の気持ちを伝えられないまま終わる
ケース3:「長女に多めに渡したい」
【遺言書がある場合】
- 「長女に現金のうち700万円を相続させる」といった個別指定が可能
- 他の相続人に不満があっても、遺留分を侵害しない範囲なら問題なし
【遺言書がない場合】
- 現金は法定割合(例:子ども3人なら3分の1ずつ)で自動的に分割
- 特別な思いや貢献は反映されない
結論:「気持ち」を残せるのが遺言の本質
⚠️【補足:遺留分と名義変更の注意点】
なお、遺言書によって特定の相続人に不動産などを単独で相続させる場合、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。
この遺留分を侵害していると判断された場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」を受ける可能性があります。また、場合によっては不動産の名義変更そのものに異議が唱えられ、登記手続きが差し止められることもあります。
そのため、遺言に基づいて不動産の名義変更を行う際には、**相続財産全体に対する遺留分の関係性を確認したうえで、登記前に専門家(司法書士・弁護士など)への相談をおすすめします。
遺言書があることで、
- もめる時間と労力が減り
- 家族の関係が守られ
- 故人の意思が「最期のメッセージ」として届く
という結果になります。
【第6章】専門家との連携で「遺言の質」は大きく変わる
専門家に相談すべき3つのタイミング
✅ 1. 財産の全体像に不安があるとき
- 借地権や共有名義の不動産など、複雑な権利関係がある場合
- 海外資産や仮想通貨など、評価・継承が難しい資産が含まれる場合
✅ 2. 相続人の関係が複雑なとき
- 前婚の子、認知した子、養子などがいる(死別や再婚など、背景はさまざま)
- 特に前妻の子と後妻の関係性は微妙になりがちで、公平感や被相続人の倫理観が問われやすいデリケートな場面も多く見られます
- 被相続人が「今の家族を大切にしたい」という気持ちは自然なものですが、他の権利者から見た際にどう受け取られるかといった“相続力”も求められます。
- 特に祖父母や親から引き継いだ先祖伝来の財産の場合、「自分の代で好きにして良い」という判断が、後々の禍根を残すケースも多く注意が必要です。
- 家族間の関係性が希薄で、トラブル予防が必要
✅ 3. 遺留分を意識した設計が必要なとき
- 特定の人に多く遺したいが、他の相続人の遺留分が気になる
- 財産の配分と想定リスクを天秤にかけてバランス調整したい
専門家に依頼する際のチェックポイント
| チェック項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 分野特化性 | 相続・遺言の実務経験が豊富か(相談事例の発信があるか) |
| 説明の分かりやすさ | 初心者でも理解できるか、質問に丁寧か |
| 料金の透明性 | 相談料・作成料が明示されているか |
| 対応の信頼感 | 無理に契約を迫らず、誠実な姿勢か |
「相談したいけど、どう動けばいい?」という方へ
まずは、
- 行政書士・司法書士・弁護士などの公式HPを確認
- 自治体や法テラスでの無料相談会を活用
- 自分の財産や家族構成をざっくりメモしてから相談する
といった“気軽な一歩”からでも十分スタートできます。
「きっちりした遺言を書かなきゃ」ではなく、 「今の自分に必要な準備を、少しずつ整えていく」 という意識が、結果的に家族の安心につながります。
よくある質問(FAQ)と想定問答集
Q1. 遺言書を書けば、相続人以外に全財産を渡せますか?
🅰️ 基本的には可能ですが、**法定相続人には「遺留分」**という取り分が保障されています。遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分侵害額請求(旧・減殺請求)が起こる可能性があります。そのため、「完全に自由」ではなく、バランスが重要です。
Q2. 公正証書遺言と自筆遺言、どちらが確実ですか?
🅰️ トラブル防止や法的効力の面では、公正証書遺言が圧倒的に安定しています。検認が不要で、方式不備による無効リスクもほぼゼロです。ただし、費用や手続きがかかるため、予算や目的に応じた使い分けが必要です。
Q3. まだ若くて元気ですが、遺言は早すぎますか?
🅰️ むしろ40代・50代こそ“相続トラブルを未然に防ぐ”意味ではベストタイミングです。特に、再婚・子どもの有無・不動産の単独所有などがある方は、早い段階で方向性を整えておくと安心です。
なお、公正証書遺言は作成後に何度でも再作成が可能です。新しいものが古いものに優先するため、まずは“今の状況に合ったもの”を作るのが大切です。むしろ40代・50代こそ“相続トラブルを未然に防ぐ”意味ではベストタイミングです。特に、再婚・子どもの有無・不動産の単独所有などがある方は、早い段階で方向性を整えておくと安心です。
Q4. 仮想通貨やNFT、ポケモンカードのような特殊な財産も相続できますか?
🅰️ 相続対象になりますが、評価や扱い方が難しい資産のため、事前に一覧や説明書を残しておくことが極めて重要です。取引所・ウォレット情報、価値の目安、第三者への引き継ぎ方法を整理しておきましょう。
Q5. 前妻との子と後妻が揉めそうです。どう対策すればいいですか?
🅰️ まずは遺言書で“誰に何をどれだけ渡すか”を明記することが大前提です。その上で、遺留分を侵害しない形で配慮を加えることや、財産の種類ごとに分割の工夫をすることで、感情面・法的リスクの両方を軽減できます。専門家のサポートが効果的です。
Q6. 親から受け継いだ不動産を後妻に残しても問題ないですか?
🅰️ 可能ですが、**先祖伝来の財産は「個人の自由」だけでは済まない側面もあります。**他の相続人からの心理的反発や道義的問題が起きやすいため、「自分の代で判断してよいか」を慎重に見極めましょう。相続力が問われる場面です。
体験談から学ぶ“備えの大切さ”を一緒に見ていきましょう。