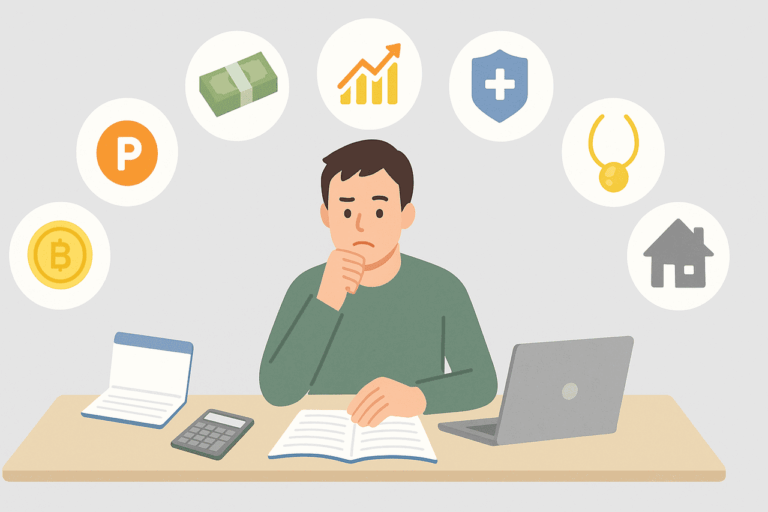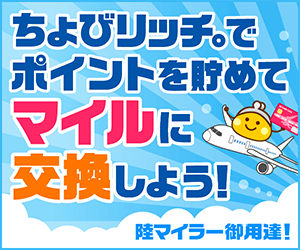【はじめに】
「遺言を書く」と聞くと、まだ自分には早い、と思う方も多いかもしれません。
ですが、“準備”としての第一歩はもっとずっと手軽なことから始められます。
それが、自分の財産や家族の情報を整理しておく「棚卸し」です。
家や預金など“わかりやすい資産”だけでなく、忘れていた契約や、普段意識していない財産まで、いざ紙に書き出してみると意外と多くの項目が見つかるものです。
今回は、“遺言を書く前にやっておくべき”棚卸し作業について、具体的なやり方と注意点を解説していきます。
※ 本記事は【第2回】「遺言書の正しい作り方」の続きです。
自筆・公正証書遺言の違いや注意点をまだ読んでいない方はこちらからどうぞ。
「遺言書さえ書いておけば安心」──そう思っていませんか? 実は、間違った形式の遺言書や中途半端な準備が、かえって家族間の深刻な争いを引き起こしてしまうケースが後を絶ちません。 特に、 自筆証書遺言を書いたが形式に不備が[…]
【第1章】まずはここから!「財産の棚卸し」とは?

「財産の棚卸し」とは、自分が保有している財産や負債を一覧化し、“見える化”する作業のことです。
たとえば――
-
どの銀行にいくら預けているのか
-
どこに土地を持っているのか
-
株式や投資信託、保険などがどうなっているのか
-
借金やローンの残高は?
こうした情報をひとつにまとめるだけでも、自分自身が現状を把握できるだけでなく、将来的に遺言を書く際に迷わずに済むという大きなメリットがあります。
また、相続時に家族が困らないように、「引き継げる形」で残す準備にもなります。
たとえ遺言書を作らなくても、「棚卸しリスト」だけでも大きな助けになります。
第2章|棚卸しすべき“7つの財産分類”と注意点
財産の棚卸しを効率よく行うには、まず種類ごとに分類して考えることが大切です。ここでは、特に相続準備を目的とした場合に有効な「7つの分類」と、その中で見落としがちなポイントを紹介します。
① 現金・預貯金(銀行口座)
もっとも基本的な財産のひとつですが、複数口座を持っている方は要注意です。
とくに最近では、メガバンク・地銀・ネット銀行などを併用している人が増えており、通帳レスの口座は存在を忘れられがちです。
-
【チェック項目】口座名義・銀行名・支店・口座番号・残高
-
【注意点】ログインIDや暗証番号も、家族に共有できるよう整理を。
② 証券・投資商品(NISA・iDeCo含む)
株式や投資信託、債券、ETFなどを保有している場合は、どの証券会社に何を保有しているのかを明確にしておく必要があります。
特に近年は「楽天証券・SBI証券・マネックス証券」など複数契約が一般的で、自分でも把握できていないケースがよくあります。
-
【チェック項目】証券会社名、口座種別(NISA・特定・一般)、保有銘柄
-
【注意点】iDeCoは証券口座とは別管理のことも多く、別枠で確認を。
③ 保険契約(生命・医療・学資など)
生命保険や医療保険などは、解約返戻金のあるタイプは相続財産に含まれます。また、死亡保険金の受取人指定がされているかどうかも重要です。
-
【チェック項目】契約者・被保険者・保険金受取人・保険会社・商品名
-
【注意点】掛け捨て型でも、契約状況をリスト化することで後々の混乱を防げます。
④ 不動産(自宅・投資用・空き地など)
不動産は相続時の分割トラブルの火種になりやすい財産のひとつです。
登記簿情報や権利関係(共有持分の有無)までしっかり確認し、所在地ごとに記録しておきましょう。
-
【チェック項目】所在地・固定資産税評価額・持分・抵当権の有無
-
【注意点】家族にとって使い道がない物件は「負動産」化の可能性も。
⑤ 動産・貴金属・美術品など
車、貴金属、ブランド品、骨董などは、評価額の明確化が難しい反面、見過ごされやすい財産でもあります。
-
【チェック項目】所有物リスト、購入価格、保管場所
-
【注意点】市場価値があるものは、相続税評価の対象になることも。
⑥ 仮想通貨・NFT(デジタル遺産)
ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨、NFTなどのデジタル資産は、パスワードを家族が知らなければ取り出すことすらできません。
この分野は、まさに“新時代の財産の棚卸し”です。
-
【チェック項目】取引所名(例:bitFlyer、Coincheck等)、資産内容、ウォレット情報
-
【注意点】2段階認証・秘密鍵・ハードウェアウォレットなど、技術的障壁の共有が必要不可欠。
⑦ 電子マネー・ポイント・マイル
楽天ポイント、ANAマイル、PayPay残高など、形式上は「財産」ではないが実質的価値があるものも棚卸しの対象に含めておくべきです。
-
【チェック項目】利用サービス名、残高、有効期限
-
【注意点】事業系アカウントと混同されやすいので区別して記録を。
初心者オーナー: 「PayPayや楽天ポイントも、金額によってはバカにならないですね。」
ナビ子: 「そうです。“使いきれなかった残高”も相続の対象と考えておきましょう。」
📝 補足:棚卸しリストの作成例(次章に続く)
「財産の棚卸し」は一度きりで終わるものではなく、定期的な見直しが推奨されます。
簡単な表形式で、自分の財産が一覧で見渡せるような「資産管理シート」を作っておくと、遺言の作成時はもちろん、もしものときにも大きな助けになります。
第3章|家族構成と相続人の確認
財産の棚卸しを終えたら、次に行うべきは「誰に引き継がせるのか」=相続人の把握と関係整理です。
● 法定相続人の基本構造
まず、民法上の「法定相続人」は以下のように定義されています。
| 順位 | 相続人の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 配偶者とともに相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 子どもがいない場合に発生 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も親もいない場合に発生 |
※配偶者は常に相続人になります。 ※養子も実子と同様に扱われます。 ※亡くなった子の子(孫)は「代襲相続」により相続人になります。
● 相続人を「関係図」で可視化すると見えてくる現実
初心者オーナー: 「うちは兄弟仲が悪くないから、そんなに問題ないと思ってたけど……」
ナビ子: 「表面上はそうでも、いざ“遺産”が絡むと考えが変わることもありますよ。可視化することで初めて“火種”が見えるんです。」
相続人を法的に確認するだけでなく、家系図や関係図を作成することを強く推奨します。 その理由は、以下のような“見えにくい人間関係の対立構造”が明らかになるからです。
- 前妻の子 vs 後妻の連れ子
- 長男夫婦 vs 次男独身
- 実子 vs 養子
- 相続放棄経験者 vs 他の相続人
こうした「見えない火種」が潜んでいるケースでは、どれだけ明確に“誰に相続させたい”という意思があっても、その通りには進みません。
● 相続人の感情に配慮しなければ、望みは叶わない
● 家族構成の図解が導く「争わない相続」
誰と誰が仲が悪いか、血縁の有無(養子・認知など)、感情的な対立の可能性、他の家族への配慮が可能かどうか…… これらは関係図として視覚的に整理することで、相続設計において致命的なミスを避ける助けとなります。
📜 コラム|豊臣秀次事件に学ぶ「被相続人の独りよがり」の末路
歴史上、もっとも悲劇的な“相続の破綻”と言えるのが豊臣秀次事件です。
一度は「後継者」として指名された秀次
関白職を甥の秀次に譲り、実質的な後継者として全国に示した豊臣秀吉。
ところが晩年、実子の秀頼が誕生したことで突如「家督を息子に譲る」と方向転換。
結果、秀次は高野山での自害に追い込まれ、その一族も皆殺しという結末を迎えます。
「俺の意志」だけで動くと家が崩壊する
この事件は、
「自分が築いた権力だから、自分の好きにして何が悪い」
という被相続人の独りよがりが、一族・政権を壊滅に導いた典型です。
現代でも、
-
晩年になって後妻や連れ子に偏った遺言
-
自分の血の子どもとの関係を軽視
-
長年の貢献を無視して、感情だけで相続配分を決定
……という事例が日常的にあります。
気づかぬうちに“現代の秀吉”になっていないか?
今こそ、自分自身に問いかける必要があります。
そして最大の教訓は「自滅の種は、身内にある」
秀吉の判断が招いたのは、秀次の死だけではありません。
彼が守り抜いてきた豊臣家そのものが、最終的に滅亡したのです。
しかもそのきっかけは、「お家騒動の混乱に乗じた徳川家」による巧妙な乗っ取りでした。
つまり――
**「最後のミス」で、どれだけ築いてきたものも一瞬で崩れる」**というのが、
この史実が私たちに突きつける最大の警告です。
✔ この章のまとめ
- 相続準備では、“財産”だけでなく“人間関係”の整理が不可欠
- 被相続人の「希望」は、相続人の感情や立場に配慮してこそ叶えられる
- 関係図を活用して「誰が不満を持ちそうか」を可視化すれば、トラブルの芽を未然に摘むことができる
- 最後に家を壊すのは、無関心・独善・準備不足の“自分自身”かもしれない
第4章「税理士は誰でもいいわけじゃない」+「調査リスク」
● 相続税の申告=税務調査の前提がある
相続税の申告は、他の税目と違い、「一生に一度」であることが多く、金額も大きくなりやすいため、
税務署側も非常に注視してくる分野です。
申告が必要になる、相続対策を検討するレベルの家庭であれば、
「税務調査はまず来る」という前提で準備しておくのが現実的です。
申告は正しく出す以外の選択肢はないといって良いでしょう。
● 相続税に強い税理士は「別ジャンル」と考えるべき
ここでもう一つ、重要なポイントがあります。
それは「日頃から顧問をお願いしている税理士にそのまま頼んで大丈夫か?」という問題です。
相続税は、法人税・所得税とは評価方法も申告手順もまったく異なり、
-
不動産評価(通達に基づく補正計算)
-
非上場株式評価
-
小規模宅地の特例
-
配偶者控除や生前贈与との調整など、専門性が極めて高い分野です。
特に不動産が絡むと、評価方法をひとつ間違えるだけで何百万単位で税額が変わります。
✔ 正しい申告をして、損も追徴も防ぐために
相続税申告は、
-
過少申告 → 税務調査で追徴+加算税
-
過大申告 → 自ら損を確定させる
という、**“ミスがすべて自分の不利益になる仕組み”**です。
だからこそ、「誰に頼むか」がすべて。
「いつもの税理士」ではなく、
“相続税に強い税理士”かどうかを確認し、専門のチームや部署がある事務所に依頼することが不可欠です。
第5章|実例で見る!棚卸しで気づいた相続トラブルの芽
財産の棚卸しと家族構成の整理ができたことで、「これで安心」と思う方も多いかもしれません。 しかし、実際にはこの段階でようやく“問題の芽”が浮き彫りになることも多いのです。 ここでは、棚卸しをしたからこそ明らかになった典型的な相続トラブルの事例をBefore/After形式で紹介します。
■ ケース1|ネット証券の存在に家族が気づかず、放置されていた
Before
故人がネット証券で保有していた投資信託や株式が、家族に全く共有されておらず、郵便物で偶然発覚。相続手続きが一部二次相続にずれ込み、二度手間・追加税務調査の可能性も生じた。
After
棚卸し時点で「○○証券/IDは○○に保管」と記載。財産目録の一項目として確実に情報を残し、相続手続きがスムーズに完了。
初心者オーナー: 「ネット証券って、郵便が来なきゃ存在に気づかないかも……」
■ ケース2|仮想通貨のウォレット情報が不明で完全凍結
Before
故人が仮想通貨を独自ウォレット(MetaMask)で管理していたが、秘密鍵や復元フレーズが残されておらず、アクセス不可で実質消滅。取引所では本人確認が不可のため、資産としての扱いも困難に。
After
コールドウォレットの所在、復元情報をまとめた紙資料を金庫に保管。棚卸し項目として残すことで、家族が確実に引き継ぎ可能に。
▼ 補足:仮想通貨は相続に向かない資産である
- ボラティリティが極端に高いため、「多めに渡したつもり」が実際には目減りしているリスクがある
- 本人以外のアクセスが非常に困難なため、相続財産としては補完的な扱いが妥当
- できれば他の安定資産とバランスを取る、別枠で管理するなど、事前設計が必要
■ ケース3|後妻への全額相続が無効訴訟に発展
Before
後妻に全財産を相続させる旨の自筆遺言があったが、前妻との子から遺留分請求が発生。結果的に遺言の内容が無効とされ、家庭裁判所での調停に発展した。
After
棚卸しと関係図を通じて前妻の子の存在と相続人としての権利を認識。遺留分を侵害しない設計+付言事項による配慮説明を加え、遺言の有効性と円満な分配を確保。
■ ケース4|実家が兄妹共有になり、誰も管理できなくなった
Before
遺言がなく、兄妹3人が実家を法定相続により共有名義で取得。売却も修繕もできず、“誰も住まない家の維持費だけが発生”する塩漬け状態に。
After
事前の棚卸しと話し合いにより、1人に集約相続させることでスムーズな売却と現金分配が実現。結果的にトラブルも発生せず、全員が納得できる形に。
✔ この章のまとめ
- 棚卸しは、トラブルの火種を早期に見つけるスクリーニング作業でもある
- 現代では仮想通貨、ネット資産、後妻問題、共有不動産が特にリスク高
- 「書き出す・話し合う・整える」ことで、“気づかぬ落とし穴”を回避できる
第6章|“これで完了”とは限らない。最後の一歩は「遺す」こと
棚卸しをした。
相続人も整理した。
揉めそうな関係性も見えてきた。
では、それをどう“残す”か。
この章では、相続準備の最終段階として、
**「誰に何を、どんな形で、どう引き継ぐか」**という視点で必要な対応を整理します。
1. 専門家を使い分ける「軸」は2つ
相続準備でよくあるのが、「どの専門家に頼めばいいか分からない」という悩みです。
ここでは、専門家を“2つの軸”で考えることが重要です。
▷ 税務対応なら税理士一択
相続税は、土地や建物など不動産を含むと評価が極端に難しくなります。
とくに旗竿地、不整形地、借地権、私道負担などが絡むと、
素人が頑張っても正確に申告するのは現実的ではありません。
さらに、相続税は申告対象になる家庭では**税務調査が「ほぼ前提」**です。
-
過少申告 → 追徴課税
-
過大申告 → そのまま納税の“損”
正確で適正な申告を行うには、相続税に精通した税理士の関与は実質的に必須です。
相続税は法人税・所得税とは別ジャンル。
事前に専門性の有無を確認しましょう。
▷ 相続争いが絡むなら弁護士に初手相談
後妻がいる、前妻の子と疎遠、遺言が偏っている──
少しでも揉める要素があるなら、弁護士の関与が不可欠です。
ただし、重要なのは「誰でもいいわけではない」ということ。
-
相続係争に強い弁護士を選ぶ(家事事件・交通事故が専門の事務所では不十分)
-
初期の段階から相談し、遺言の設計段階で予防策を講じる
-
行政書士への依頼は、争いが起こらない家庭限定
2. 遺すべき“記録”と“書類”
準備だけで満足せず、「残された家族が“使えるように”する」のが相続準備の本当のゴールです。
以下の書類・資料を整えておくことで、安心と実効性が確保されます。
▷ 財産棚卸しリスト
→ 銀行・証券・保険・不動産・借入・仮想通貨など、全項目を一覧化
→ 紙+データの二重保存が安心(印刷+USBやクラウド)
▷ 家系図・相続関係説明図
→ 相続人の範囲、代襲相続、相続放棄の有無などを明示
→ 遺産分割協議書や手続き時にも使用される
▷ 遺言書(公正証書がおすすめ)
→ 自筆証書は安価だが不備リスクあり
→ 公正証書は安全性が高く、トラブル予防効果も高い
▷ 付言事項(想いの言葉)
→ 感謝・補足・理由づけなど、「気持ちを伝える」ことで争いを防ぐ
→ 法的効力はないが、精神的な影響力は非常に大きい
▷ 保管と共有の工夫
→ 金庫保管、家族分散、信託銀行・専門家への委託など
→ 「家族が見つけられる形」で保存しておくことが大前提
ちゃんと届くように残してこそ、あなたの相続準備は完了するんです。
3. +αの備え(必要に応じて)
相続準備をさらに万全にするために、以下のような選択肢も検討可能です。
-
死後事務委任契約:葬儀、SNS解約、ペット引き取りなどを信頼できる人に委任する契約
-
家族信託・任意後見:認知症リスクや長期的な資産管理が必要な場合の法的備え
これらは専門家との相談で検討することが望ましいですが、“こんな制度がある”ことを知っておくだけでも安心感が違います。
第6章まとめ
-
相続準備の最終段階は、「残すこと」
-
税理士と弁護士は、それぞれの専門性で切り分けて依頼すべき
-
書類を作るだけでなく、「誰に伝えるか、どう使われるか」まで設計することで、本当に意味のある相続準備が完成します。
💥「準備は完璧だったはず…」でも起こる相続トラブル。
その原因と、回避のヒントを次回で解説します。