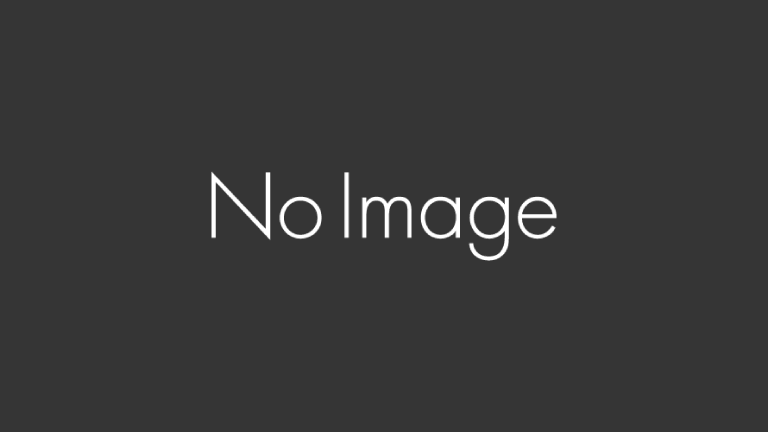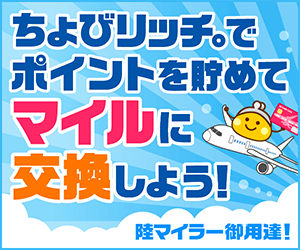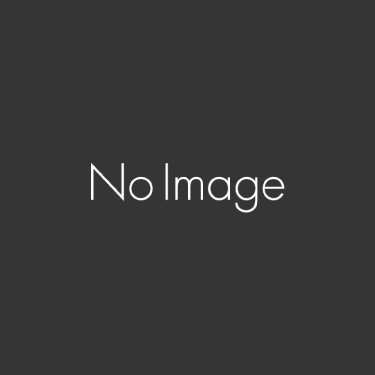今回は、実際に棚卸しを行ったことで明らかになった典型的な相続トラブルを、Before/After形式で紹介します。
「備えておけば避けられた」
「意外と見落としていた」
そんな実例を通して、トラブルを未然に防ぐ視点を深めていきましょう。
※ 本記事は【第3回】「遺言前にやっておくべき“棚卸し”と家族構成の整理」の続編です。
棚卸しのやり方や注意点をまだご覧になっていない方はこちらからどうぞ。
【はじめに】 「遺言を書く」と聞くと、まだ自分には早い、と思う方も多いかもしれません。ですが、“準備”としての第一歩はもっとずっと手軽なことから始められます。それが、自分の財産や家族の情報を整理しておく「棚卸し」です。 家や預金など“わ[…]
ケース1|ネット証券の存在に家族が気づかず、放置されていた
Before
故人はネット証券に複数の口座を開設し、株式・投資信託を中心に運用を行っていたが、相続人には一切知らせていなかった。郵送通知はすべて「ペーパーレス設定」にしていたため、自宅に明確な証拠も残っておらず、死亡後数か月たっても誰も気づけなかった。
After
相続人が故人の確定申告書類を整理中に、過去のeメールに残っていた証券会社からの「分配金通知メール」を偶然発見。そこから口座の存在が明るみに出たものの、既に口座は凍結されており、手続きには複数の書類提出と時間が必要だった。最終的には資産は無事に移管されたが、相続発覚が遅れたため、株価の変動や分配金の受取損失が発生していた。
補足)ネット証券の多くは、相続人からの申出がない限り自発的に相続開始を感知しません。そのため、放置されていても資産は会社側に把握されず、時間と共に休眠状態になる可能性も。手続きには戸籍謄本や相続関係説明図、印鑑証明などが必要で、煩雑なうえに時間がかかることも多いため、早期発見が肝要です。
教訓ポイント:
- ペーパーレス化により「見える資産」が見えなくなるリスクがある
- ネット証券の棚卸しには「定期的な通知先」「ログイン情報」も併記すると良い
- 相続開始後は、故人のPC・スマホ・メールから証拠を探すしかない場合も多い
ケース2|仮想通貨の秘密鍵が分からず資産が消失
Before
40代で急逝した故人は、投資目的でビットコイン・イーサリアムなど複数の仮想通貨を保有。安全性を重視して、コールドウォレット(インターネットに接続しないハードウェア型の保管方法)に資産を保存していた。ところが、秘密鍵(アクセスに必要な文字列)を書き残すことも、家族への説明も一切していなかった。
After
遺族は仮想通貨の存在自体は把握していたが、秘密鍵の所在が不明でアクセス不可。問い合わせ先も明確に存在せず、事実上“誰も開けられない金庫”と化し、数百万円相当の資産が凍結されたまま放置。結果的に、資産は相続財産としても評価できず「なかったこと」になってしまった。
補足)仮想通貨は銀行預金と異なり、アクセス情報=資産そのものです。故人の生前管理がすべてであり、亡くなった瞬間に第三者が介入するルートはほとんど存在しません。法的に資産と認められていても、技術的に取り出せなければ意味がなく、「消えてしまう財産」となり得ます。
教訓ポイント:
- 仮想通貨の相続には「秘密鍵の伝達」が絶対条件
- 保管方法(取引所型か、ウォレット型か)で難易度が大きく変わる
- 生前に「仮想通貨資産ノート」などで最低限の共有が必要
ケース3|後妻と遺留分を巡るトラブル
Before
高齢男性が再婚し、再婚相手と二人暮らしの中で新たな人生を送っていた。遺言書では「すべての財産を後妻に遺贈する」と記載。前妻との間に子どもが二人いたが、疎遠で数十年連絡がない状態だった。
After
相続開始後、前妻の子が遺留分を主張。後妻側は遺言書を盾に「争う姿勢」を示すが、最終的には裁判を避けて和解金支払いで決着。後妻が取得予定だった不動産の一部を売却して現金を工面し、感情的な対立だけが残った。
教訓ポイント:
- 再婚・前婚子ありのケースは「遺留分請求リスク」が極めて高い
- 遺言+事前説明(遺言執行者や話し合い)で軟着陸が望ましい
- 法的対策だけでなく“感情面のフォロー”が重要
ケース4|共有不動産が“塩漬け”に
Before
郊外にある築50年の一戸建てを、相続人3人で共有。誰も住まず、修繕もせず、税金と草刈り費用だけがかさむ状況に。売却も検討されたが、兄弟姉妹の一人が「思い出があるから売りたくない」と強硬に反対。
After
売却・管理・利用のいずれも進まず、固定資産税だけが毎年発生。近隣からの苦情も出て、最終的には行政代執行寸前に。裁判所による共有物分割請求を視野に入れるも、精神的・金銭的負担が大きすぎて頓挫。
教訓ポイント:
- 共有不動産は「売れない・動かせない・揉める」の三重苦
- 単独所有+代償分割が一番現実的な分け方
- 感情と法的手続きの両方を整理する必要あり
この章のまとめ
- 棚卸しは“問題のタネ”を見つけるための作業でもある
- デジタル資産は“存在を知る”こと自体が最大のハードル
- 形式的な遺言や名義変更だけでは解決できないリスクが潜んでいる
最終回【第5回】では、実例をもとに、家族を守る遺言と専門家の選び方を詳しく解説します。